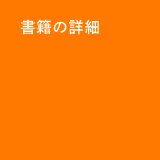新版 日本の未来へ
──司馬遼太郎との対話(仮題)
ジャンル[総合・歴史・文明論]2015年発行予定
四六判上製 ページ数未定
定価:未定
ふらつき続ける無層社会日本
“日本人は志を喪失したのではないか!”
海図なき漂流の時代、混沌とする閉塞の時代をどう生きるのか。
同時代を生きた[知の思索者]ふたりの貴重な対話!
地球時代の混迷を超えて、民族と国家、そして日本及び日本人について論じ合う。
◆日本文明の危機
司馬 とにかく日本人は上等になることですね。上等にならないと日本人はこれから生きて行けないかもしれません。/物事を識別して統合する心の働きですね。
梅棹 大切なのは知恵でしょうね。/たとえば、企業の中でもいろいろ問題があるでしょう。そこで大局的に事態をとらえる訓練が必要になります。その中で明日を考える能力が求められる。これはまさにイデオロギー中心の時代とは正反対です。
私は21世紀の日本は非常につらいことになると見ています。どうも日本文明はいまが絶頂ではないでしょうか。
司馬 残念ですが同感ですね。衰退期にむかっているという証拠に、日本文明の現在の構成者が少しものを考えなさすぎるように思いますね。
梅棹 現在はこういう幸せな社会ですから、考えなくてもいいんです。だから、あまり危機感がありません。しかし、21世紀の中ごろはひどいことになるかなと、私はかなり危機感をもっています。
(本書より)
「司馬遼太郎はわたしの30年来の友人である。かれとは、たびたびともに飲み、ともにかたりあった。そのこころよい記憶をわたしはおもいかえしてたのしんでいる。それらのかたりあいのおおくは私的なおしゃべりではなく、新聞や雑誌での対談として、のちに活字になって公表されたものである。(中略)かれとの交友をなつかしみつつ、それを記念するために、わたしはこの本をつくる決心をした。」
(本書「まえがき」梅棹忠夫 より)
「梅棹と司馬の対談から構成された本書は、同時代を生きた独自な眼をもつ思索者の交点を明示する記録として重要な意味がある。今後、この交点の意味と行間にひそむメッセージをさまざまな視点から読みとくことが必要になってくるであろう。そこから、あたらしい風景の探索がはじまるからだ。」
(本書「付論──知の饗宴」松原正毅 より)
[内容構成案]
| 新版について──歴史の旅人と知の狩人と[松原正毅] | |
| まえがき[梅棹忠夫] | |
| 第I部 | 司馬遼太郎から梅棹忠夫へ |
|---|---|
| 第II部 | 民族と国家、そして文明 |
| 第III部 | 日本および日本人について |
| 第IV部 | 追憶の司馬遼太郎 |
| 付論1 | 梅棹忠夫──幻視の行為者[松原正毅] |
| 付論2 | 司馬遼太郎──裸眼の思索者[松原正毅] |
| 付論3 | 同時代の思索者──司馬遼太郎と梅棹忠夫[米山俊直] |
| 付論4 | 知の饗宴──梅棹忠夫と司馬遼太郎の対話[松原正毅] |
| あとがきにかえて──知の先導者との出会い、そして[松原正毅] | |
梅棹忠夫(うめさお・ただお)

国立民族学博物館・梅棹資料室にて(1997年頃)[撮影:河野 豊]
1920年、京都市生まれ。1943年、京都帝国大学理学部卒業。1944年から、モンゴル、アフガニスタン、東南アジア、アフリカ、ヨーロッパなどで、民族学的調査に従事。京都大学人文科学研究所教授、国立民族学博物館長を経て、同顧問、名誉教授、(財)千里文化財団会長。京都大学名誉教授。理学博士。朝日賞、国際交流基金賞などを受賞。文化功労者。文化勲章、勲一等瑞宝章受章。専攻は、民族学、比較文明学。
著書に『モゴール族探検記』『東南アジア紀行』『サバンナの記録』『文明の生態史観』『知的生産の技術』『地球時代の日本人』『日本とは何か』『情報の文明学』『実戦・世界言語紀行』『世界史とわたし』『行為と妄想』など多数。「梅棹忠夫著作集」(全22巻別巻1)が刊行されている。2010年 死去。
司馬遼太郎(しば・りょうたろう)
1923年、大阪市生まれ。1943年、大阪外国語学校蒙古語科卒業。産経新聞大阪本社文化部長、出版局次長を経て退社。「ペルシャの幻術師」により講談倶楽部賞受賞。『梟の城』により直木賞受賞。以降、菊池寛賞、毎日芸術賞、吉川英治文学賞、日本芸術院賞(文芸部門)恩賜賞、読売文学賞、朝日賞、新潮日本文学大賞、NHK放送文化賞、読売文学賞随筆紀行賞、大仏次郎賞などを受賞。文化功労者。文化勲章受章。
主な文化論・文明論に『手掘り日本史』『歴史の舞台』『人間の集団について』『アメリカ素描』『長安から北京へ』『微光のなかの宇宙』『風塵抄』(全二巻)『春灯雑記』『この国のかたち』(全六巻)『街道をゆく』(全四十三巻)などがある。1996年 死去。
米山俊直(よねやま・としなお)
1930年、奈良県に生まれる。三重大学農学部卒業。京都大学大学院農学研究科修士課程修了後アメリカ・イリノイ大学社会人類学部大学院研究助手として文化変化の通文化的比較研究に参加し、文化人類学を学ぶ。帰国後、京都大学大学院農学研究科博士課程単位修得退学。甲南大学助教授、京都大学教授、放送大学教授、大手前女子大学学長、大手前大学学長を経て、国際京都学協会理事長。京都大学名誉教授。農学博士。今和次郎賞、京都新聞文化賞などを受賞。紫綬褒章、瑞宝中綬章受章。専攻は文化人類学。
著書に『米山俊直の仕事 人、ひとにあう。』『米山俊直の仕事 ローカルとグローバル』『「日本」とはなにか』(いずれも人文書館)など。2006年 死去。
松原正毅(まつばら・まさたけ)
1942年、広島市に生まれる。京都大学文学部卒業。京都大学大学院文学研究科修士課程修了。京都大学人文科学研究所講師、国立民族学博物館教授、国立民族学博物館 地域研究企画交流センター長・教授を経て、現在、坂の上の雲ミュージアム館長。国立民族学博物館名誉教授。専攻は、社会人類学。
著書に『遊牧の世界』(中央公論社)『トルコの人びと〜語り継ぐ歴史のなかで』(NHKブックス564)『遙かなる揚子江源流』(共編)『青蔵紀行』(中央公論社)『遊牧民の肖像』(角川選書)『人類学とは何か』(編)『司馬遼太郎について』(共著、日本放送出版協会)など。